投稿日:2025年09月19日 BLOG
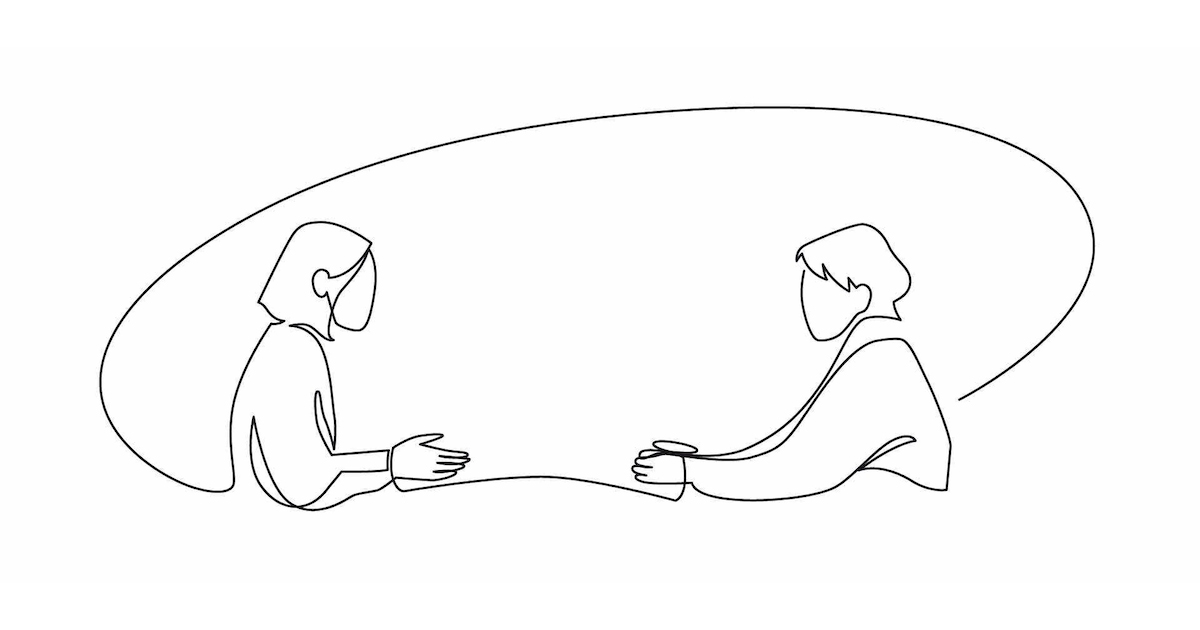
会社内でコーチングを活用しようとするとき、想定される場面は、日々の業務中や1on1ミーティングの場面が考えられます。そして、そのときの対象者は、自ずと自分の部下や後輩に絞られてくるのではないかと思います。
本日は、その対象者が若手社員である場合、特に1on1ミーティングの場面において、コーチングをどのように活用したら良いかについて考えてみます。
部下が若手社員であり、仕事に対して意欲的・前向きであるときは、コーチングは活用しやすいと考えられます。その際、上司は、部下の話をしっかりと聴き、認め、部下の内省が深まるような質問を投げ掛けていくことが求められます。
前述の「認める」や「聴く」や「質問」は、いずれもコーチングスキルとしてすでに体系化されており、言い換えれば、上司はコーチングスキルを身につけてさえいれば、部下のモチベーションが高いかぎりコーチングが機能しやすいと言えます。
とはいえ、若手社員ゆえに知識・経験不足は否めない点もありますので、その際は、上司が適度に提案や情報提供、また、体験談などを伝えてあげることにより、部下の思考の整理をサポートするように心掛ける必要があります。
では、部下が若手社員で、仕事に対してのモチベーションが低いときはどうでしょうか?
ある意味、コーチングがもっとも機能しにくい状態と言えるかもしれません。
コーチングが機能するのは、上司と部下との間に信頼関係が築けていることが前提です。
なので、関係性がまだ築けていないようでしたら、日頃の関わり方もそうですが、1on1ミーティング開始時に雑談などを行い、リラックスした状態になってから本題に臨むように努めます。
部下はモチベーションが低いゆえに、なかなか意欲的・前向きに取り組めないこともあるでしょう。とはいえ、仕事ですから「じゃあ、仕方ないね」ということにはなりません。
そのような場合は、基本的なコーチングスキルを活用することはもちろんですが、ときには上司から要望事項を伝えたり、部下に期限を決めて取り組ませたりするなど、ある程度の強制力を発揮する必要があります。
そうなると、もはやコーチングとは言えないのですが、そもそもコーチングは手段であって目的ではないので、場合によっては割り切って強制力を発動することが肝要です。
あと、大切なのは、その後のフォローアップです。
フォローアップは、通常、翌回の1on1ミーティングの冒頭に行います。
フォローアップでは、上司と約束した行動をきちんとできているか、できている場合はしっかりと認め、できていない場合は何が原因でそうなったのかを考えさせることが求められます。
これらを習慣化していくことで、部下は考えて行動する習慣が徐々に身につくようになり、さらに成功体験を通じてモチベーションも徐々にアップしていくようになります。
若手社員に対してコーチングを活用したいと考えている方には、是非一度、GCS丸の内校の無料体験講座にお越しください。
あなたにお会いできることを楽しみにしています。

現代人の多くは、必要な“モノ”は一通り持っています。
このことから、人々の欲求は、次第に“モノ”から“コト”へと移行しつつあり、それに連動するかのように、人々の価値観は、“結果”から“プロセス”へと移行し始めています。
現代においてコーチングが支持されるのは、私たちコーチが、「クライアントとパートナー関係を築くことにより、クライアントの目標達成までのプロセスを管理できる専門家」だからと言えるのではないでしょうか。
コーチングオフィス エン代表 大石 典史